リレーエッセイ - 『ふと思う』


J.N.Henpek
『ふと、思う』 ~トーラーヤーハーン~ №38 J.N.ヘンペク 特別寄稿
とらやはんの西神学校設立の旨意
来た 見た 喋った 笑った 泣いた 癒された
「なにか、せんとあきまへんなぁ」。「ほんまですなぁ」。「そやけど、何したらよろしゅますやろ?」。「それがわかったら苦労おまへんわな」。「ほんなら、今日はこのへんで」。「ちょーっと、待ったりぃな。
それでは身も蓋もおまへんやないか」。
「センター教会も月一回の礼拝だけやのうて、平日に神学生や信徒が自由に参加できるゼミ・青年活動みたいなものをやりたいね」。風呂釜牧師の呟きがあった。風呂釜とは湯(ゆ)だけ。ゆーだけ。言うだけの人のことである。
「ありきたりな感じですが、キリスト教基礎講座はどうでしょうか。経験者が未経験者に、牧師が信徒・未信者に知識を伝達するような場ではなく、参加者が平場で根本問題を対話の中で掘り下げていくような空間と時間を提供してはどうでしょうか」。「そら、ええ考えや、『君』がそれをやったらええ」。
気の利いた講座の名称が模索された。「センター教会併設神学校ちゅうぐらいの大法螺が必要やな。この場所が『とらや』の西側にあるから『とらやの西神学校』ちゅうのはどうや」。風呂釜牧師が命名者を気取る。「センセ、呼び捨てはいけません。『とらやはん』と言うべきです」。花鳥風月牧師が恐る恐る提案する。
『とらや』は、近所の甘党の大学創始者と少なからずの因縁がある。『とらやはん』の響きは、『トーラーヤーハーン』とへブル語みたいに聞こえる。風呂釜牧師が、こじつけて、『戒・神・恵』と解読する。実務担当の『君』は困惑するばかりである。
『ふと思う』 ~全国キリスト教学校人権教育セミナー~ 鳥井新平 №37
8月11日~12日に大阪梅田にある関西学院大学梅田校舎を会場にした人権教育セミナーに参加してきた。
全国各地からキリスト教学校の教育にかかわる者70名あまりが参加した。今回で35回目を数える。
初回は10名たらずの小さな会だった。大阪の矢田の解法会館を会場にして、部落差別と在日韓国朝鮮人と障害者に関する教育について、
情報交換と研修の場をもったのがはじまりだ。
参加者も増え、分科会も必要に応えて、これまでのグループに加えて、平和教育や性的少数者、人権教育入門、複合差別・・・と内容の充実をみた。
プログラムも開会礼拝からはじまり、派遣礼拝に至るまで、基調講演や聖書研究、そして分科会(会によっては現場研修)と盛りだくさんだ。
カトリック、プロテスタントと超教派で仲良く違いを楽しみながら運営されているのもとてもいい。
私は今回は複合差別の分科会で学ばせていただいた。在日コリアンでありかつ女性であることが二重の差別を受けているという実態を深く学ぶことができた。
1:人権教育とは「思いやり」や「やさしさ」を育むといったムード的なものではなく、国際法や条約で守られた権利を道具として、
どのように具体的に適用させて共生社会を創っていくのか、ということがとてもよく分かった。
2:若い世代の保守化・右傾化の現状とどうしたらいいのか、という悩みが教育と直結した深刻な課題であることも認識できた。
さて、教会はどうするか?参加者の一人がオレンジ色の水筒を前に、「私はオレンジ色を取り戻したい」と言われた言葉が脳内でリフレインしている。
私は何をとりもどし、何を創ろうとしているのか、とふと思った。
『ふと、思う』 ~山上の説教~ 菅 恒敏 №36
現役時代はかなりのお酒の愛飲家だった。例えば、お酒なしで食事をとる時はご飯の味がまるで砂を噛むように不味く感じられて、おおよそお酒なしで食事をとることは考えられない位であったが、病の身になってからはカロリー制限のため飲酒を控える様になり、それ以来夕食のおかずの次第で、気分的に飲みたいときは少し嗜むという習慣になった。
この様な状況になってから、とくに空腹で喉の渇きを覚えているときに飲むビールの味は格別である事に気が付いた。逆に、十分に食事をとって満腹状態のときや飲み物を沢山飲んだ後に飲むビールの味は苦くて不味い。この事に気が付いたとき、ふと思った。そうだ、これだ!と
聖書の中の「山上の説教」として広く愛されている有名な言葉の一つ、「心の貧しい人は幸いである」(新約聖書:マタイによる福音書5章3節)は、まさに空腹時や喉の渇きを覚えているときに飲むビールの美味さを指しているのだなと。
心の状態が何らかの理由により寂しさや悲しみ、或いは苦しみの余りに、何をする気力もなく心が空っぽの状態のときこそ、イエス様の言葉(救い)が容易に入ってきて、心や体の隅々まで行き渡り、新たに生きる力の源となり得ることを例え話で示されたのだ。「心の貧しい人」は容易に救いに与ることが出来るから「幸いである。」と仰ったのだなということがよく分かった。
イエス様は当時の心の貧しい人たちの置かれている位置や心情をよく理解されて、その様な人たちの一人でも多くがご自分の救いに与れる事を願っておられたに違いない。現在社会でも「心の貧しい人」は世代を問わず沢山おられるが、果たしてその人たちにイエス様のこの例え話が届いているのだろうかと、ふと気になった。
『ふと、思う』 「外にでよう!と、ふと思って」 2025年7月7日 井上勇一 №35
2023年の教会スローガンは「外へ出よう!」であった。その時から、月1回、教会の有志で、NPO「ほっこり」と共催して「みんなでカレーを食べる会」を開催している。この7月で30回を数えた。参加者は「ほっこり」から3名、教会から4名位が集い、30食分のカレー、スープ、サラダと果物を作り、子どもは無料、大人は300円で提供している。
東九条、東寺道と河原町との交差点近くにNPO「ほっこり」の食堂兼事務所があるが、
地域が様変わりする中で、地域内外からも遊びがてら立ち寄って、カレーを食べて頂く。NPOにとっては、地域住民や子ども達とのつながりをつくるためにとの目的を持ち、教会にとっても地域社会・子ども達とのつながりをつくりたいとの願いの中で、活動をするに至った。
つくるカレーは、市販のルーを使ってのもの、ちょうど教会の愛餐会のカレーである。特別に凝ったものではない。ただ、ホッコリでの居心地がよいのか、皆さん「美味しい」と言って食べてくれる。
今、教会は社会との接点を失っている。「うちは保育園をしているから、幼稚園をしているから」と社会との接点があるかのように語るが、外から保育園に通う保護者はだれも保育園のとは考えるが、教会のことなど考えてはいない。教会自らが「動き出すこと」、「関わりもっていくこと」が求められている。
また、NPOもボランティアを求めている。NPOは社会貢献と自立が持続への道と活動している。ボランティアは大歓迎である。「カレーづくり」もNPOからの要請である。今、
教会は、金曜日の朝8時~10時半、「モーニングコーヒー」を手伝い始めた。見切り発車なところもあるが、「老体でもできること」をと願い通っている。
『ふと、思う』 ~ 糞ったれ ~ 柳井一朗 №34
5月30日、私の大学生の時の指導教員のお連れ合いの召天3年記念日でした。
晩年、この方のお連れ合いは、私が働いている教会のすぐ近くの病院に入院されいた時期があった。
恩師から、「病院で妻の介護をしていて、離れられないのでので、何も食べていない。何か買ってくるように」と電話連絡を受けた。
私は学業が全くだめだったので、突然の恩師の電話に驚いた。懐かしい思い出の一つではある。
この恩師のお連れ合いのお父さんは、今年亡くなられて70年の節目を迎えられた。
この方は、美術品、南蛮美術の収集家であられた。
6月15日まで、神戸市立美術館で収集された美術品、資料、写真が展示されています。
よく知られている収集された美術品のひとつが、茨木市千提寺の隠れキリシタンのお宅から、
昭和初期に買い求められた「ザビエル」の肖像である。
私は5月30日にこの美術館を訪問した。
館内展示品の一つに、
恩師のお連れ合いが幼少の頃、お父さんと一緒に写っていると思われる写真を見つけた。
この収集家は、神戸教会員だった画家、小磯良平と親交があったと思われる。
小磯による晩年の収集家の自画像油絵もまた印象に強く残った。
この収集家の戦後の自筆の原稿の一節に、戦前、戦後の美術収集に対する、国の理解の変遷を憤慨されていた。
戦後、それら収集品に莫大な税が掛けられて、維持困難になり、すべての収蔵品を神戸市に寄託される思いも書かれていた。
その心境は一言「糞ったれ」であった。
日本は戦争に負けた。一時この国を占領した国の考えが、税に反映されたのかもしれないとも思った。
そのことは、今日、教会創立100年以上経過した教会が境内地、礼拝堂、教会の維持に困難を極めていることにも
繋がっているような気がした。
『ふと、思う』 ~ 上の句、下の句 ~ 鳥井新平 №33
世界中の教会で、2000年を超える歴史の中で、1つの礼拝説教を「二人羽織」のようなことをしている「不届き者」の礼拝はないと思う。それを受け入れてニコニコと、時に神妙にお聴きいただいて礼拝に参加してくださっている殊勝な方々もこれもまた異例のことではないか。上の句を岸本兵一牧師が詠んで、下の句を私がつける。そして、「揚げ句」を視聴者・参加者の皆様が個々人の祈りで仕上げる・・といったいわば連句のようなこの礼拝形式はある種の実験ではないか、とフト思う。
私が36年間働いた近江兄弟社学園は創立者一柳滿喜子が「ここは教育の”実験場”です」と言っていた。実験は成功することもあれば、失敗することもある。彼女の伴侶・ヴォーリズは、『失敗者の自叙伝』をのこした。建築・医療事業・薬品会社・輸入業・文書伝道・・・あれほどの事業を「神の国」をつくろうと奔走した自分のことを「失敗者」と呼ぶユーモラスな表現の奥に隠れた無垢な信仰に頭がさがる。
願わくば、上の句の作り手である岸本牧師があまりに前衛的な句で大暴れすることなく(その際は句が苦になる)下の句の作り手の弟弟子のことを思いやって礼拝に臨まれることを。
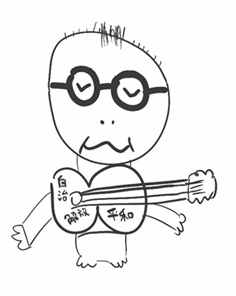
イラストby 佐々木結
(次回 柳井一朗)
『ふと、思う』 ~地球の温暖化を防ぐ~ 菅 恒敏 №32
岩手県大船渡市で大規模な山林火災が発生した。3.11の東日本大震災後14年目を控えての大惨事で、震災後復旧・復興の道半ばの出来事であり、被災された方々の落胆の思い如何ばかりかと案じつつも、1日も早く適切な支援が届けられ、平穏が戻ることを祈るばかりである。
山林火災は大勢の人員配置に加え、多数の消防車・ヘリコプターなどの出動により懸命の消火活動が続けられたが、9日間延焼が続き全く手の付けられないような状態であった。幸運にも10日目に雨が降り、その雨によって延焼は食い止められ、12目に鎮火宣言がなされた。人間の力では9日間掛かっても手の付けようがなかった延焼が1日の降雨で止まったことを知り、自然の力の大きさを改めて思い知らされた。大昔の人達はこの様な自然の偉大さに畏敬の念を抱き、そこに神信仰というものが生まれたに違いない。科学万能の時代に生きる私たちは、自然に対する畏敬の念を失い、神も忘れてしまっている。
最近、山林火災が多発しており、その後岡山・愛媛の他に韓国・アメリカでも大規模な火災の発生が報じられている。その原因の一つに地球温暖化が指摘されており、温暖化のために空気や山林が乾燥し、燃えやすくなることによるとされている。地球温暖化は山林火災のみならず、大雨・異常高温・暴風・雪害などの自然災害をもたらすため、今や世界的な重大事であるにも拘わらず、温暖化抑止の目標ラインにはほど遠い状況である。
地球温暖化は、人間が自然への畏敬の念と神の存在を忘れ、ひたすらに自分の生活の便利さ・豊かさを追求する余り、自然を破壊し汚し続けてきたこと(地球温暖化ガスの発生増加)によるとされている。そのことに思いを馳せながら『ふと、思った』。地球温暖化から地球を守るための最良の方法は、大昔の人達のように自然への畏敬の念を取り戻し、神のもとに立ち返って、人間の本来の姿を取り戻すことではなかろうかと。
『ふと、思う』 ~必ずや、つながる~ 井上勇一 №31
毎月1回、礼拝を捧げて、100回を数えるようになった。伝道所としての歩みを重ね4年目を迎える。教区センター教会は、「ここに教会を立てる」との霊の導きを受けて、主にある京都教区の諸教会の「祈り」をもって、設立した。第2種教会設立、宗教法人の設立、教会財産の移管など現実的な課題を背負いつつの「祈り」であるが、継続し祈り続けることで克服できればと願っている。
イエスは「あなたがたが地上でつなぐことは、天上でもつながれる」(マタイ18:18)という。教会という交わりを神の導きを受けて創り出すとき、イエスは「二人、三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいる」という。この「人と人とがどのようにつながるのか」、このつながり方が教区センター教会においても課題となっている。
この3年余り、教会は「隣人を愛し、人に仕える。神を愛し、教会に仕える」ことを教会の宣教指針として歩んできた。この間、対面での礼拝と配信による礼拝とを行ってきたが、自立教会にまで至っていない。今後も「協力会員を募り」、「協力牧師を募り」、「支援教会への派遣」を続けて自立をめざすが、今もう一つの課題が生まれてきた。
それが、「継ぐ」ということである。わたしも75歳を超えた。残りの人生を教区センター教会に賭けたとしても、役員会のメンバーは、80を超えた者、75を超えた者2名、そして60を超えた者で構成されている。今「つながる働き」を「どう継いでいく」か、課題が生まれているのである。ただ、イエスは「わたしの名で集まれば、その中にいる」と約束している。ならば、「必ずや、つながる方が生まれる」と、ふと思うのである。
『ふと、思う』 ~実りと収穫~ 柳井 一朗 №30
立春、節分、境内地夏みかん収穫、
七十二候の第一候、新年がやってきたという
実感がこみあげてきます。
25年の間に、夏みかんの実が上質に豊かに
実るようになりました。
みかんの木への愛情と言葉がけに尽きると密かに思っています。
2本の木のうち、北側の1本が豊作でした。
南側の木はお休みでした。豊作の年の翌年は木は休みます。
このご時世でもなお、毎年成長が求められる人間界において、
人は生きることに疲れてしまいます。
収穫したみかん1個は木に残します。
神さまに感謝をささげます。
一部は野鳥に与えます。輪切りにします。野鳥は半日できれいに食べつくします。
一粒も残さず、きれいに食べます。
センター教会、4月20日 復活日、第100回礼拝
を迎えます。実りの帰属は神さまです。神さまの
畏敬の念を抱き、聖霊の働きをひたすら信じて、
祈り続けて、第2種教会設立を覚えて、
この教会に連なって参りたいと思っています。
冬芽が教えてくれたこと 菅 恒敏 №29
冬の寒さの間も天気の良い日は、健康管理のために近くの京都御苑に散歩に出かけている。秋には赤く黄色く、きれいに色づいていた木々(落葉樹)の葉は全部落ちてしまい、今は寂しく無造作に裸の枝を伸ばしている。この枝々の先には、すでに春になれば新しい葉や花となるための芽(冬芽)が出ている。
冬の寒さの間、冬芽は次の春がくるまで静かに眠っていると思われているが、実は木の1年間の生活サイクルの中で、冬芽の時が一番忙しいとされている。それは、春が来れば一斉に葉を出したり、花を咲かせるための準備をしておかなければならず、そのために小さな体の中で大忙しの作業を行わなければならないからである。文字から感じられる限りでは、冬芽は静かに眠っている様に思われるが、実は一番忙しい時を過ごしている事を知った時、何かレントの時のイエス様のご受難の姿と重なるところがあるのではと『ふと、思った』。
イエス様はレントのご受難の期間中、全ての活動を休んで、誰からも邪魔されないように弟子達のそばを離れて、一人静かに祈りの時を過ごしておられたとされているが、この祈りの時は、あたかも木々の冬芽が冬の寒さに耐えながら、春の訪れの時の準備のために大忙ししている状景の如くに、罪深い人の世の暗さ・冷たさに耐えながら、我ら罪人の救いのために、一心不乱に祈り、慟哭の時を過ごされていたのである。まさにレントは、イエス様の生涯の働きの集大成の時となる、大忙しの時であったのだ。
このことに気付づいてからは、一心不乱に祈られるイエス様のご受難の姿に今更ながらイエス様の愛の深さ・大きさを思い知らされた思いである。まだ少し先のことではあるが、今年のレントを迎える日(3月5日~4月19日)には、冬芽が教えてくれたことを思い出しながら、イエス様のご受難の姿を偲びつつ、新たな思いでレントを迎えたいと願っている。
まっ直ぐ、歩きなさい 井上勇一 №28
10月に75歳を迎えた。32歳で牧師になり、70歳位までその働きが出来たらと願っていたが、その歳を超え久しくなった。牧師は自らの働きを自覚しつつ、その務めが終わったと判断した時、「隠退する」の決断をする。そう思いながら今に来ている。
11月15日に内視鏡による大腸検査を受けた。8個のポリープが見つかり、7個を切除し、1個のポリープを残した(1個は年明けに入院し切除する)。20日頃に風邪をひき、38度の熱となり、その後に血尿をし、度々と続く。この歳には前立腺肥大など様々な泌尿疾患が予想されるが、これが75歳という齢ではと知るのである。
私たちは誕生があれば終わりがある。私たちはこの宿命を負って生きる。ただ、「老い」は、加齢する中でただ老いていくのではない、患いをし、身を細るようにして、徐々に枯れていく、これが老いるということではなかろうか。最近、よく言われるのは、「まっ直ぐ、歩きなさい。」である。私の歩いている姿をみた妻の弁である。
ただ、加齢し続ける身体に対して、私たちの「こころ」は違う。こころに浮かぶ思い、願いは、「まだできる」という心意気である。そこには「先々に夢が生まれ、希望が芽生える」、そして、私のこころを駆り立てるのである。
これからの一年、一年は、「身体とこころ」の按排(あんばい)ではないか、と思う次第です。
そこで ヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って
罪の赦しを得させるために悔い改めの洗礼を宣べ伝えた
これは 預言者イザヤの書に書いてあるとおりである
荒れ野で叫ぶ者の声がする
『主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ』
ルカによる福音書3章3~4節
変わらないもの 柳井一朗 2024年11月17日 №27
10月下旬、30年通っているコーヒー店の支店が建て替え開業した。2年半休業であった。小生普段は本店に通い、その支店にはたまにしか行かない。支店建て替え開業一週間前、店から連絡受けて、その支店でコーヒーを飲み、新規企画の朝食を食べた。カウンター席、会計場所、売店の位置はおおむね変わらず、店舗入り口の客の動線は変えているのに、客には、以前の店と変わらないという印象を持たせるような雰囲気をぷんぷん発散させていた。25年前の本店建て替えの時にも同じような印象をもった。
支店の開業記念品をもらった。その記念品には、英語表記で「全面建て替え」とは違う、「改装記念」という意味の英語表記が用いられていた。極めて恣意的で、意図的であると感じた。
話は変わるが、ヨーロッパ車は型が変わっても、いつまでも変わらない雰囲気を持たせている。 よくわからないが、変わっているのに、変わっていないとう法則に従ったある戦略があるのではないかとも思う。本店でそのことを伝えた。そして、「客がうるさいからではないか」と問うても、「お客様によって支えられて」の一点張りだった。従業員教育が行き届いていると感じた。
支店の旧店舗の入り口床に埋めらていた金文字の店舗名は、丁寧にはがされ、支店新店舗、新規二階席の「想いでの棚」に飾られていた。この件は私が働いている教会でも同じ手法を用いている。このコーヒー店の創業者は絵画を描かれる方だったので、今まで拝見したことのない「厨房の壁にかけているフライパン」の油絵が二階に新たに飾られていた。
昨日、本店でコーヒーを飲んだ。本店と支店の雰囲気、客層が違うことに気づいた。そのことを店に伝えたら、その通りだと言われた。それ以上は聞かなかった。贔屓客は味が変わらいという。しかしそれは違うとも思う。時代とともに、生きている人間の価値観、味覚は刻々と変化しているわけで、味は変わってきているはずである。 しかし、客は「変わらない味だ」という。
教会は二千年間、同じ聖書からみ言葉を聴いている。同じ内容であるが、受け止め方は時代時代で違うと思う。しかし、人は教会で聴く内容が変わらないという安定感、安心感も望む。そのことがすべてだとは思わないが、時代の只中での聖書の言葉の聴き方を提供しつつ、変わらない味を演出する。老舗店舗の取り組みと似ていると、コーヒーを飲みながら、ふとそのようなことを思った次第である。
牧師館の尾曲がり猫 トト 入 治彦 2024年10月20日 №26
ふと、思うのは3年半前に亡くなったうちの猫トトのこと。大阪にいた時、夜半玄関先で啼き続け、妻が根負けして家に入れました。体重500g程度でネズミに毛が生えた位の大きさでした。試用期間があると感じたのか、輪っかを作るとその中をくぐって行ったり来たりし、紙で小さいボールを作って投げるとくわえて戻って来ました。そこで、映画『ニューシネマパラダイス』の主人公の名前をとってトトと名付けて家で飼うことに決めました。地域の子どもたちの集団登校、下校時になると門の上に乗ってその送迎をするので、子どもたちも「トト!」と呼びかけていました。
京都に来てからも妻が「庭のクルミの木のセミたちの鳴き声がうるさくて寝てられない!」と叫んだその10分後、シャーシャー鳴いているクマゼミをくわえて返って来たこともありました。コタツにあたってテレビドラマを見ながら「うちには子どもがいないからなあ」と言った途端、私の腹にドーンと体当たりしてきたものがありましたが、トトでした。「オレがいるじゃないか!」と怒っていました。夫婦げんかをしていると、間に入って「にゃめろ!」と言って仲裁に入ってきたこともありました。私とかくれんぼもしました。7キロ近くまで大きくなり、犬と勘違いする人もいたほどです。
一度牧師館の2階の階段からもんどり打って転げ落ちたことがあります。高齢でしたから、ああ死んだんじゃないか、骨折したかと心配しましたが、大丈夫でした。しかし、翌日大阪北部地震が発生し、京都も5弱でかなり揺れたため、あれは身を挺しての予告だったのかと思いました。他にも不思議なことはたくさん起こりました。子どもたちや大人たちからも愛され、中には彫像を作ってくれた教会員、絵を何枚も描いてくれた子どもの教会の子もいます。晩年は児童館の子どもたちが毎日とりあいで抱っこしていました。
トトは、黒白のハチワレ、エメラルドグリーンの目をした尾曲がり猫でした。当初いじめられ骨折したのかと思っていましたが、後でそれは尾曲がりとかカギしっぽとも言い、幸運をカギしっぽに引っ掛けてくる猫だと知りました。22年、人間で言うと105才。早朝私たちを起こして妻の腕に抱かれ、空気をつかむように右手をあげ伸びをして亡くなりました。もともと野良でしたが、黒地の背中に白の二つの斑点が天使の羽のようで、神様が牧師館に住めと送ってきた猫のように思いました。3年半経った今も感謝しかありません。
燧ヶ岳登山 菅 恒敏 2024年9月15日 №25
現役時代、山登り仲間と尾瀬ヶ原の探索に出かけた。その日の朝、尾瀬の近くに名瀑があるとのことで、その滝巡りに行った際に、「燧ヶ岳登山口」という案内板が目に留まった。未だ元気盛りだった私たちは、非常食や登山装備など何の準備もないままの姿で無謀にも燧ヶ岳に向けて登山を始めた。登り始めてから分かったことだが、そのコースは意に反して難コースで、岩山をよじ登るような急坂部が多く、しかも途中で雨が降ってきた。雨具の備えもなく、びしょ濡れの状態で、一休みしようと休憩タイムをとっても寒くて寒くて、何の備えもなく登山を始めたことを後悔したが、もう後の祭りであった。
大げさな表現かも知れないがその時は決死の思いで、何とか頂上にたどり着き(燧ヶ岳の標高:2346メートル)、互いの無事と頂上にたどり着けた喜びを分かちあっていたのもつかの間、悪天候のために急に雲海が湧き出して、たちまち辺りの眺望が効かなくなり、下山口が分からなくなってしまった。この時は、さすがに一瞬「遭難」という恐怖感が頭をよぎり、仲間一同うろたえていたところ、幸いにも下から登ってきた一人の登山客の姿が雲海から現れ、そこに下山口があることが分かり、そこを足がかりに何とか無事に下山することが出来た。
この事件以来、無装備・無計画な無謀な登山は行わないよう心掛けるようになったのは当然のことであるが、現役時代に登った数々の山の中で、この燧ヶ岳の登山行は、その意味でも楽しさを越えて特別に心に残るものであった。
或る時、たまたま燧ヶ岳登山行を思い返していたとき、ふと、思った。あのとき、雲海の中に現れて私たちに下山口を教え示してくれた登山客は、イエス様ではなかったかと。びしょ濡れ状態の寒さの中で、道に迷い、恐怖と不安に直面していた私たちに下山口を示し、救って下さったのはまぎれもなくイエス様だったと。
悲しみを超えて 井上勇一 2024年8月18日 №24
異常気象の中なのか、ここで3名の方がつぎつぎの召された。
7月30日に多芸正之牧師、
31日に高木恵子さん、
8月4日に酒井哲雄牧師である。
多芸牧師は西小倉めぐみ教会を設立し、めぐみホームを立ち上げていく。
その宣教は新しい教会像をつくり上げる活動をした。
高木恵子さんは京都基督教福祉会児童発達支援センター洛西愛育園の園長として活躍し、
統合保育を各保育園に普及させた。
酒井哲雄牧師は大阪YMCAを舞台に阿南キャンプセンター、六甲YMCAを作り、
社会活動リーダーの養成に努め、晩年は児童福祉従事者養成に尽力をさせた。
3名の先生たちの働きを通して知らされるのは、「新しさ」である。
今までの働きを土台にして、そこに新しい考え方を取り入れてひとつの方法を創り出す。
教会が2000年もの間、延々と生き続けた背景には、
宣教の働きの上に新たな手法を取り入れて、積み重ね続けた中に今の教会がある。
今教会は低迷する状況下に置かれているが、
そんな中で新しさを求めた取り組みが散見される。
この「新しさ」は既成の枠組みを超えた働きがあるし、
聖書に描かれる「キリスト者の群れ」(使徒11:26)に回帰している感がある。
宣教8年を迎えた「京都教区センター教会」宣教は、
この「新しさ」を求めた「働きではないか?」と、ふと思うのである。
編者注
それから、バルナバはサウロを捜しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。
二人は、丸一年の間そこの教会に一緒にいて、大勢の人を教えた。
このアンティオキアで初めて、弟子たちがキリスト者と呼ばれるようになった。
使徒言行録11章 25~26節
2024年7月13日記 柳井一朗 2024年21日 №23
嘱託講師で通っている学校の通り道、狐坂では、毎年6月中旬から蝉が鳴き始める。
私が住み込みでは働いている教会では、本日、今年はじめて蝉が鳴いた。夏が来たと思った。
京都に長年住んでいると、祭りに直接かかわらなくても、7月は特別な思いがする。
30年育てている檜扇は、ここ数年来、やっととというか、とうとう祇園祭りに合わせて、開花するようになった。
30年かけて、京都の檜扇となったのである。
親しくしている音楽家がその人の人生の節目で今春、自動車運転免許証を取得された。
近所に住んでおられるので、この間、近くの交差点で、初心者マークをつけたその本人が運転する車と隣同士になった。
窓を開けて、手を振ってあげた。
その車は夫人の所有する車で、登録番号は音楽家バッハの数字表記となっている。
バッハに心酔していると思われる。京阪神にもう一台、バッハの数字表記の車がある。
私は、僭越ながら、その音楽家に、
「自動車の運転においては、奥さんのほうが、経験者なのだら、
奥さんの言うことをよく聞いてあげてください」と言い放った。
この音楽家は人格者ではあるが、、しかし、奥さんの言うことは聞かないと思った。
なぜなら、人間とはそのような存在であるから。
終わり
編者注
※数秘術 ヌメロロジー(numerology)
バッハ(BACH)B=2 A-=1 C=3 H=8 2+1+3+8=14
ヨハン・セバスチャン・バッハ J.S.BACH 9+8+2+1+3+8=41
よって、車の№は、1441と推測
雨のレクイエム 入 治彦 2024年6月16日 No22
ある日のこと、仕事が終わってソファに座ってテレビでもみようかと、リモコンのスイッチを入れたところ、いつまで経っても画面が映らない。どうしたのかと思っているうちに、なんだか部屋の中が涼しくなってきたというか寒くなってきて、テレビのリモコンではなくて、エアコンのスイッチを押していたことに気づいた。
別の日の礼拝後、委員会も終わって牧師館に戻ってみると、妻が「これ、爪切れない」と言っている。よく見るとそれはホッチキスだった。
こんなことなら良いけれど、妻が「教会のホームページの口コミにこんなこと書かれている」と言ってスマホを持ってきた。見たら「この教会の歴代牧師はメルセデス・ベンツに乗っている。特技はお茶たて」誰がベンツやねん?うちの教会事務のSさんじゃないか。うちはマーチだよ。
間違えということで言えば、『Al W A Y S三丁目の夕日』の映画でも一般的にも知られるようになった西岸良平の漫画『三丁目の夕日』?夕焼けの詩?の中の『雨のレクイエム』を想い出す。
ある女の子が弟を連れて、梅雨の雨の日、近所の池に魚とりに出かける。池に着いて網を使って魚を獲ろうとしたところ、弟は足を滑らせて溺れ死んでしまった。お姉さんは弟の手を握って引き上げようとしたけれども、ズルズルと沼に吸い込まれていく弟を助けることはできなかった。それ以来、女の子は自分のせいだったと殻に閉じこもって学校にも行けなくなり、家でいつも寝込み休んでいた。周りの人たちも池に祟られたのではないかと思っていた。
それから1年後、雨の降る日、家の縁側に河童の子どもがひょっこり現れた。「キュウリを1本ちょうだい」とせがむ。河童の子はキュウリを食べ終わると、その家の家族のことをしばらく尋ねてから、帰って行こうとした。「雨、雨、ふれ、ふれ、母さんがじゃまめでおむかえ、うれしいな??」と歌いながら。女の子は弟がいつも蛇の目をじゃまめと間違えて歌っていたこと思い出し、弟の名前を呼んだ。河童の子は、振り向いて「ぼく、おねえちゃんのこと、大好きだよ」と言ってそこからいなくなった。という話。池で溺れた子は、河童の子になって帰ってくるという伝説があると聞く。
それにしても、中森明菜の歌に『雨のレクイエム』という曲があったことは今日まで知らなかった。
私にとっての原風景 菅 恒敏 2024年5月19日 №21
今年の春も加茂川の両岸の桜並木を堪能することが出来た。私は開放感に溢れ、心の和む加茂川の眺望に特別の愛着を抱いている。とくに出町辺りの橋の上から上流に向けての眺めが格別で、遠近図法の手本の様に展開する眺めは、単に美しさのみならず、幼いころからのいろんな思い出が一杯詰まってもいる。当時は、加茂川は水遊び・魚取り・蛍狩りなどと、格好の遊び場でもあった。
遠方の山並みはアルプスの様に高くそびえる山ではないけれど、若い頃は山並みの美しく揃った山景に向かって「山の彼方の空遠く、幸い住むと人の言う」とのワーズ・ワースの詩を口ずさんだりしながら、遙か彼方に希望の光を感じたりしていたこともあった。
暫くの間、京都を離れるようなことがある場合でも、京都に戻ってきて加茂川の眺めを見ると、「やっと京都に帰ってきた!」と安堵感に浸ることが出来る。この様に、私にとって加茂川は四季折々の風景の美しさのみならず、幼少の頃からの思い出の詰まった川、何時も心に安らぎを与えてくれる川として、いわば私の心の「原風景」となっている。
この様なことを自問自答しながら、『ふと、思った』 さて、自分には加茂川とはまた違った別の「原風景」があったのではないか、と。そうだ、それは中学生時代に京都教会で信仰告白式を受けたときの一景だ。
その時の情景を思い出すと、若い頃の初々しい気持ちと新鮮な思い一杯に信仰告白を決意したときのことがまざまざと思い出されるとともに、私の信仰を育んでくださった方々の姿が懐かしくまぶたに浮かび、今なお私を励ましてくださる。まさしく今の信仰生活にとっての、否人生そのものの原点であり、大切な「原風景」と言える。寄る年波を口実に、体力も気力も衰えるままに怠惰な生活に陥りがちな日々を前にして、これからは加茂川の風景に霞んでしまわないよう、もう一つの「原風景」を大切にしていかねばと心を新たにしている。
目はかすまず、活力も 井上勇一 2024年4月21日 No.20
今年、75歳になるが、よく牧師隠退について考えることがある。牧師もそうであると思うが、神の召命によって今があるとなれば、牧師も生涯が終わるまでその召命・働きがあると理解している。モーセは「神から約束の地に入ることが許されず」、ピスガの頂から約束の地を眺めその地で召されていくが、「神からの許しがなかった」ことが自らの召命の終りと受け止め、自らに与えられた務めを終え、同時に死を迎えるのである。モーセが召されたのは120歳であったが、「目はかすまず、活力も失せていなかった」とのことである。
モーセは全イスラエルの前に歩み出て、これらの言葉を告げた後、こう言った。
「わたしは今日、既に百二十歳であり、もはや自分の務めを果たすことはできない。
主はわたしに対して、『あなたはこのヨルダン川を渡ることができない』と言われた。
申命記1章 1-2節
モーセがどれほどに健康に気づかい、身体を鍛えていたか分からないが、120歳という天命をもって神に仕えたこと、そこには神の配慮があってのことと受け止める。そこへ行くと、75歳になって「目はかすみ、活力も失せ、物忘れがひどく」身になり、周りから心配されるようになり、身の引き時を考えていかねばと思うようになった。
そんな中で、「ふと思う」ことは、「それでは、この先、お前はどう生きるのか」という問いである。趣味もない、ただ仕事を続けてきた者にとって、時間がポッカリと空き、ボーとたたずむ自分を想像すると、何ともやるせない。牧師や園長を他者にお願いしても、「地域にこだわり、仲間とやりたいことを細々と続けて生きる」、それしかないと思うこの頃である。ただ「いつ牧師を辞めるか」は、自分自身、神と向い合う中で、決めていきたい。
「ふと、思う」 柳井一朗 2024年3月17日 No.19
「センター教会創立以来3回目の復活日を迎えるにあたり」
~キシモト牧師が焼かれたパンをめぐる実践神学省察~
今から25年前くらい前、キシモト牧師はよく燻製鮭をつくられた。
人生の悲哀を感じさせるほど良い塩梅であったと記憶する。
只今、キシモト牧師は「フリークッキー」と「聖餐のパン」を焼かれる。
センター教会は広域伝道圏伝道信徒交流のもとに伝道牧会を続けている。
キリスト教会乙訓コイノニア、福知山教会、大江野の花教会と
先のクッキーとパンがささげられている。
いまだにキシモト牧師の「フリークッキー」をお菓子と勘違いしている人が
教区内に一定数いることは、大いに残念なことである。
先週の土曜日、私が働く教会にキシモト牧師のパンが贈られてきた。
この日朝から小生は不在。宅配業者が気を利かせて、礼拝堂の聖餐台の上に、
このパンを置いてくれた。
この聖餐台には「主の恵み深いことを味わい知れ」と刻印されている。
直近日曜日、再開20年続けている月一度の夕礼拝にこのパンをささげた。
佐川淳さん率いるヴォーカルボイスの声楽と聖書朗読だけで、
受難節夕礼拝をおこなった。
礼拝後、この聖餐台に載せたキシモト牧師のパンを皆で囲んで、
立ったままで、食べた。
コーヒーと、小生が作っ
たキシュまがいの卵焼きを添えた。
「主の恵み深いことを味わい知れ」とは、
これが極意であることに今頃になって初めて気が付いた。
これが小生の実践神学の省察である。
『間 』 入 治彦 2024年2月18日 No.18
先日私たちの教会の1階平屋の建物のテラスに大きなサルが座っていたという。私は実際目撃していないけれども、遊びにやって来ていた中学生数名が見たと言っていた。少し以前より、京都の中京区近辺にサルが二匹出没していたことは聞いていた。東山の方からやって来て御所にでも棲みついたのだろうか。
2年ほど前にも、東大路丸太町から京都市役所経由で、東洞院三条付近新風館前で、
女性一人を怪我させたイノシシが走り回り、警官に捕えられた。本州では、ツキノワグマが人里に現れて人家の柿を食べていく。ドングリが不作だったためとも聞く。北海道ではヒグマが家畜や人間を襲ったりもする。この冬は暖冬でクマがなかなか冬眠していないらしい。
以前より、急激な宅地造成によって、野獣の棲んでいる山と人の住んでいる間にあった緩衝帯の里山がなくなってきていることが指摘されている。
そういえば、季節においても、春と秋が短くなって季節のグラデーションがなくなってきて、四季が夏と冬の二季になってきているともいう。極端な話、車を運転する時、朝は暖房、昼は冷房ということもあり、砂漠化か、間のクッションがなくなってきている。
コロナ感染流行によって対面でコミュニケーションをとることが難しくなり、その分礼拝のオンライン化や会議のZoom化などが進んだともいえる。しかし、対面による情報、共に食事をとって話をするコミュニケーションに比べれば心もとない。色々なことが早くなった反面、相手の立場になって考えるとか、テキストはあっても、発言の背景にあるコンテキストを想像するといったアナログ的な余裕に欠けることもあるのではないだろうか。人間関係もクッションがなくなり、直接的、デジタル化しているところはないだろうか。
ルカによる福音書17:20?21には「ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。『神の国は見える形では来ない。<ここにある><あそこにある>とも言えるものではない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ』」とある。
井上洋治神父は、『余白の旅』の中で「神は余白に宿る」と語っていた。間にいます神を感じつつ日々過ごせればと願っている。
ノアの箱舟 菅 恒敏 2024年1月21日 No.17
新聞に2023年度は今までで一番気温の高い年であったと報じられていた。思い起こせば、昨年は5月下旬頃から夏の暑さが始まり、秋になっても気温は下がらず、四季のうち春と秋がなくなり、夏と冬だけの二季になってしまった。また、12月の或る日の天候は、北の北海道では大雪、日本海側は大雨、西日本は晴天下で春の暖かさといった天候の極端な地域差に加え、降れば大雨、吹けば暴風といった天候異変の極端化が当たり前になってきている。
しかもこのまま放置すれば天候異変の極端化はひどくなる一方だとも言われており、暴風雨による家屋の破壊・土砂災害・人命への危害、高温による健康被害に加えて、近年ではでサンマ・イワシが獲れなくなったり、果実の不作、米質の低下等、食料被害にまで及び、このままでは人間の生存権が脅かされるとの不安に駆られながら「ふと、思った」。
このような事態と同じようなことが過去にあったっけ。そうだ! 神のことを忘れてやりたい放題の人間を滅ぼそうと三日三晩雨を降らし続け、神を忘れなかったノアの一族だけを救われたという、旧約聖書の「ノアの方舟」の話だ。このとき神は「もう二度とこのような形で人間を滅ぼすようなことはしない」と約束されたと記されている。
地球温暖化は人間が際限なく便利さと豊かさを求めた結果、消費エネルギーが増えて温暖化ガスの放出が増加したことが原因とされており、「ノアの方舟」の再来を想起させる今日の気候変動の危機は、人間が神の領域を越えて、自ら招いた事態であると言える。全ての人々の生存権と平和を守るために、今こそ私たちは神の許に立ち返り、温暖化抑止に力を合わせ、知恵を出し合っていかなければと痛感している。
新たな課題が 井上 勇一 202312月17日 No.16
教会では、11月、聖徒の日の前後、2か所の墓地で墓前祈祷の時をもつ。一つは若王子墓地、もう一つは深草墓苑である。
教会の墓地とするのは若王子である。若王子には教会創立頃に召された20代の若い人たちが3名葬られているが、その後、召された方の遺骨は、家族の墓地へ納めるもの、深草墓苑に納めるもの、そして教会に預けるものとなる。ですから、教会には6~7体の遺骨を与かり、土へ帰っていく日を待っている。
墓碑を若王子山に整備し、そこに納めたら、問題のすべてが片付くのであるが、教会員、遺族の方もなかなか縦に首を振らない。理由は、墓地が若王子山の頂にあること、高齢者が中心の教会にとって、山に登っていくには「少々どころか、シンドイ」のである。60代の頃は、しっかりした足取りで登った私であるが、最近は「息を切らして」登り、降りてくる。
前に登った仲間も、一人減り二人減りと、「ヒザが痛い」と遠慮をする。
教会に与かる遺骨、その召された方々は、「車で行ける場所をと願っているのだろうか」と「ふと思う」のである。そういえば、深草墓苑は、車で行ける快適な場所にある。
洛南に来て20年を超えた。いくつかの課題をみんなでのり越えてきたが、ここへ来て、
新たな課題が生まれている。どうしたものかと「ふと考える」のである。
『ふと、思う』 2023年11月12日記 柳井一朗 No.15 202312月17日
~すぐ執筆順番がまわってくるような気がする。小生が年齢を重ねたからか~
井上勇一牧師が天の声を聴かれて以来、センター教会前身の集会が開始した。
昨年の春、教区のお赦しをいただき、教区センター伝道所(教会)が開設され、一年半が過ぎた。主任説教教師、キシモト兵一牧師と出会い、師と仰ぎ今日に至っている。ひょっとすると聖書に書かれている教会も始まりはこんな感じであったのかもしれない。
ところで、私が住み込みでは働いている教会の境内地、今秋、クリスマスツリーの木、小さい方の枝垂れ桜、ライラックを切り倒した。原因は今夏の暑さによる。
このクリスマスツリーは20年以上育て、毎年待降節を迎えるとこの木を鉢に移植して、礼拝堂で1月6日まで用いることを繰り返した。
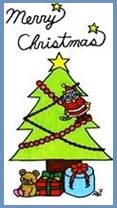
このクリスマスツリーは死んだ。日本語が母語でない人から「木は枯れた」という日本語ではないかと指摘された。「あなたの言う通り」。しかし、私はこの木と共に生きたのだから「この木は死んだ」という日本語が私の心境を表していると言ったら、分かったような?わからないような?顔をされた。
さらに境内地には二本の夏みかんの木がある。毎年この頃になると明け方の冷え込みで、みかんは黄緑色からみかん色へと変貌する。しかし今夏の暑さで、みかんは強烈な西日で大やけどを負っている。今までに見たことのない光景だ。
わたしはなんでもかんでもいつもと違う様子をすぐに「異常」というのは嫌いだ。しかし、今夏の暑さはどうやら「異常」であったことを認めざるを得ない。
地震、雷、火事、親父 入 治彦 2023年10月15日 No14
幼い頃、祖父とお風呂に入ると、祖父が決まって「地震、雷、火事、親父」とつぶやいていたのを思い出します。その頃、私は家から1キロほど離れた「朝鮮人山」と呼ばれる小高い丘の雑木林に行って、カブトムシかセミ取りをしたことがありました。そこには20基くらいのお墓があり、当時まだ見たこともない文字、漢字でもひらがなでもなく、ローマ字でもない文字が刻まれていました。
祖父にその話をすると、昔関東大震災があって、100キロ離れたここからでも東京の方の空が真っ赤に見えて、大きな火事だというのがわかったと教えてくれました。その後「朝鮮人が井戸に毒を入れた」というデマが埼玉の方まで流れてきて、自警団や官憲が朝鮮人とおぼしき人を捕まえては、トラックの上で彼らの首を切って虐殺していったと語っていました。「朝鮮人山」とは、その人たちを追悼する墓だったのかと後で知りました。実際朝鮮人、中国人、方言の違いから日本人も含めて約6000人が殺されたと伝えられています。私の地元では86人の方々が殺されたという記録が残っています。
今年は関東大震災から100年の節目の年であり、マスコミでもこの大量虐殺、ジェノサイドの問題が頻繁に取り上げられています。京都教区は、25年前から韓国基督教長老会大田老會と交流を続けていますが、私も2回程大田老會を訪れました。彼らの教職の中には、この問題について研究している人もいて、あの時かの内村鑑三まで弟子に朝鮮人がいたにもかかわらず、自警団の夜警に加わっていたというショッキングな話も教えられました。
マルコによる福音書5:1~20に「悪霊に取りつかれたゲラサの人をいやす」という記事があります。墓場を住処とし、鎖で縛っても引きちぎり、足かせを砕くので誰も彼を繋いでおくことができなかったと伝えられていますが、イエスは近づいてきたこの人に向かって「名は何というのか?」と尋ねました。彼は「名はレギオン。大勢だから」と答えています。レギオンとはローマの戦死した五千から六千人の大軍団であり、イエスの言葉にいたたまれなくなった悪霊たちは、豚の大群に乗り移り、湖に落ちて自滅しました。イエスとは群れている者に対し、1対1で対し、単数化して癒す方でもありました。
私たちもまた、昨日は軍国主義、今日は民主主義、明日は経済第一主義と、時代の大多数による共同幻想に踊らされ惑わされやすいものですが、「おまえの名は何というのか」と問われる者として日々歩んでいきたいものです。
病院の待合室 菅 恒敏 2023年9月17日 No13
私は丁度6年前に「慢性腎不全」になっていることが分かり、それ以来3ケ月毎に定期検査を受けるために某大学付属病院に通うようになった。大学病院ということで、組織の規模も大きく、病の治療若しくは検査のために来院者も多い。曜日によっては、病院内が来院者で溢れかえっている時もあり、世間にはこんなに健康に支障を来している人が大勢おられるのかなと驚きでもある。
来院者は若い世代の人もおられるが、多くは高齢者で、私の教会の年代別教会員の構成比:若年世代の人がおおよそ10%、、中年世代の人30%、高齢世代の人60%とほぼ合致するなと計算してみたりしている。来院者の中には車椅子や手押し車を利用したり、杖をついたり、または連れ添いの人に手を取ってもらったりと、歩行に支障を来している人も結構多い。病の苦痛のみならず、日常生活に支障を来していることは辛いことである。 そして、来院者の表情の多くは暗くて不安げであり、何か希望を失ってしまっているかのように見える。来院者の表情が暗いのは、至極当然のことと自分を振り返ってみてもその訳はよく分かる。単に検査を受けるだけでも、何か悪い結果が出ないか、別の病変が出てないかと、検査結果を知らされるまではびくびくして、不安で落ち着かない。他にもっと重い病気を患っている人にとっては、もっとその不安は大きいだろうし、今罹っている病気が果たして治るのかどうかという先のことの不安、生活の保障への心配といったことなどが重なって、どうしても表情は暗くなり、希望の光が見えないものになってしまい勝ちである。
このような病院内での有様を目の当たりにして「ふと、思う」。
「聖書には『医者の必要な人は私のもとに来なさい』 とのイエス様の言葉が記されているが、来院者の皆さんは果たしてイエス様(キリスト教会)を知っているのだろうか」と。
洗礼を授ける 井上勇一 2023年8月20日 No12
私は、京都刑務所で教誨師をしている。2019年に委嘱されたので5年になる。刑務所は、4メートルの超えることができない壁で閉ざされ、外と内とで生活がガラと変わる。
外は自由な世界、内は規律と自由のない監視された世界である。最近、滋賀刑務所がその働きを終わり閉所されたが、刑期を果すために入所する人間は少なくなり、全国的に犯罪が減少しているとの事である。とのことである。教誨師を初めた頃は「聖書研究」のようにして「集合教誨」をしてきたが、2年前から礼拝をしている。簡単に式次第をつくり、賛美歌、聖書朗読、話、そして最後は、自由な祈りの時を持ち、主の祈りをみんなで祈って終わる。讃美する時、初めの頃は一人で歌っていたが、この頃はみんなで歌うようになった。祈りの時、真剣に祈る姿に接するが すすり泣く姿をみる。
個別教誨というのもある。一人、30分程度面談するのであるが、よく相談されるのが、「洗礼を受けたい」という申し出である。教会に行った経験がある者、外国籍の者、いろんな背景をみるが、長く拘束を受けるということで、そこには心の拘束が生まれるか、孤独と先々の不安に苦しむのだろうか、重い相談である。
洗礼を授ける。それは神と洗礼者との関係で、受洗者が神の子となる誓約式である。それは、どこであろうが為せる業と言える。ただ、受洗者は教会に所属するとなると、少し整備が伴う。新しく生まれた「教区センター教会」であれば、受洗者を受けれる教会とならないか、「ふと、思う」のである。
※教誨師(きょうかいし):prison chaplain(プリズン チャプレン)
『いつ、病気をなさったり、牢におられたりするのを見て、お訪ねしたでしょうか』 マタイによる福音書25章39節
牧師館日記 2023年7月11日 柳井一朗 2023年7月16日 No11
7月11日朝、小生が働いている教会の境内地で蝉が初めて鳴いた。
今年1月上旬と7月上旬、身元引受人を務めた二人の韓国留学生が帰国された。
教会の北隣と南隣のマンションを下宿先として紹介した。
一人の留学生の親は今年早春、大田老會・京都教区との交流で京都に来られた。
二人の両親には、京都で会う機会が与えられた。
二人共、日本のことをこよなく愛してくれている。
7月に帰国した留学生は兵役のために一時帰国した。
「京都は第二のふるさと」と言われ、祇園祭りの花・檜扇の鉢物を寄贈をされた。
2026年に日本に「帰る」と言われた。
留学生見送りの後、関空出国カウンターの端っこでひっそり営業している「一村一品」の売店に立ち寄った。
1月にミャンマーの靴ベラ、7月にチュニジアの鍋敷を買った。
「ふと、思う」神学は、井上勇一の提唱を受けて、岸本兵一が進化させた教区センター教会に帰属する宣教姿勢である。「ふと、思う」が今後、「広域伝道圏信徒交流ネット」の広がりにつながることを祈り願いたい。
Fine del mondo 入 治彦 No10 2023年6月18日
世界においしいという言葉は数限りなくあることと思う。たとえば、韓国の「マシッソヨー」中国の「ハオチー」、ネパール語の「ミートチャ」、英語の「デリシャス」、フランス語の「セボン」、ドイツ語の「レッカー」などなど。私は趣味の一つがイタリア文化なので、そのおいしいという言葉が結構気になるのだが、テレビC Mなどでは、子どもがほっぺたに人差し指を立ててねじるようなポーズをとりながら、「ブオーノ」と言っている様子がよく映し出される。しかし、このポーズを大人はとらず、大人はむしろ口先に親指と人差し指で輪っかを作り、投げキッスをして「ブオニッスィモ」と叫ぶ。でも、もっとおいしい場合は、最高!という意味で「オッティモ」というようだ。「スクイズィート」(ほっぺた落ちそう)他にもいくつか表現はある。
ところがどっこい、最近もっとすごい表現があるのを知った。それは「フィーネ・デル・モンド」直訳すれば世の終わりということ。少し意訳すれば「おいしすぎて死んでもいい!」「死ぬほどおいしい」位の表現だ。野球などでは「ピンチがチャンスだ」ということもあるが、このFine del mondoにはなぜか両義性というか宗教的なものを感じる。
中世キリスト教界では、「デ・ノヴィッスィマ」という言葉も使われた。ノヴァなる英会話学校もあるが、あれも新しいとか新星といった意味があるようだが、その絶対最上級で最も新しいということ。それは他と比較して新しいではなく、世の終わりから最後から考えることが最も新しい意味のようだ。
「パッション」という言葉も情熱という意味の他にJ.S.バッハのマタイ受難曲をドイツ語でマトイス・パッションというように受難という意味もある。全然違うような意味なので興味が湧く。
初めて伝道師として赴任する時のこと、主任牧師との面接で「君はどんな教会を作りたいと思っているか」と尋ねられた。特にイメージはなかったので思いつくままに「サーカス小屋のような教会です」と答えた。当時世間は第一次漫才ブームであり、文化人類学者の山口昌男の本ばかり読んでいてトリックスターに興味を持っていた頃だった。ちょうど「サーカス-アクロバットと動物芸の記号論」という本も読んでいた時だった。
牧会から1年離れていた時、イタリアのサーカス学校に行って道化師の修行をしたいと思っていたことがある。二世牧師の同級生にそんな話をしたら「牧師も道化師みたいなもんやで」と言われたのが今でも強く記憶に残っている。
蝶の姿に教えられる 菅 恒敏 2023年5月21日 №9
我が家の猫の額のように狭い庭にみかんの木が植わっていて、毎年アゲハチョウが卵を産みに飛来する。春と秋の2回の飛来分を合わせると、40匹分以上の卵が産み付けられ、そのまま放っておくと雀や他の野鳥の餌食になるため、飼育箱に入れて飼育することにしており、数が余りにも多い時は教会の児童館に引き取ってもらったりしている。
アゲハチョウが卵から孵化したときは、鳥の糞のような色姿(鳥の目から逃れるための擬態とされている)であるが、何回か脱皮を繰り返して緑色の美しい青虫に変身し、やがて蛹を経て、成虫として華麗なアゲハチョウに羽化するまでの、いわゆる変態と成長の課程を眺めているのはとても楽しく、私の息抜きのための趣味の一つになっている。
アゲハチョウは、春に孵化して夏前に蛹になって羽化するものと、秋に孵化して冬前に羽化するものがあり、さらに冬前に蛹になっても寒くなって羽化が間に合わなくなったため、春になって暖かくになるまて蛹のまま冬を越すものがある。そして、夏の蛹は周囲の緑色の葉の色に似せて緑色になり、秋の蛹は周囲の枯れ葉の色に似せて茶色になって、擬態によってちゃんと身を守る術を心得ており、虫といえども実に賢い。
我が家の飼育箱の中にも蛹のまま冬を越すものが何匹か残り、そのうちの3匹が4月16日の朝、申し合わせたように一斉に羽化して青空に向かって元気に飛び立って行った。今年は例年になく蛹の羽化が遅かったので、冬の間異常に気温の低い時期があったため命を失ってしまったのではないかと心配していたが、無事に羽化したのでほっとした。
蛹のまま冬を越すアケハチョウは、動くことも話すことも出来ないまま、春の訪れをひたすらに信じ、時の流れに身を任せて、じっと寒さに耐えながら春を待ち望む。その姿を見て『ふと、思った』 私たち人間は、コロナ禍やウクライナの戦争、物価高騰など、暗いことばかり続く今の世の中を嘆き、「早くこの様な状況を収めて下さい」と天に向かって祈る。でも、祈りは容易に聞き入れられず、不安は募り苛立ちを覚える日々であるが、ジタバタしないで静かに春の訪れを待ち望むアゲハチョウの姿に、己の信仰の足りなさを教えられる思いである。
これは学びなのか 井上勇一 2023年4月16日 №8
牧師は料理をする。よく言われるが、周りにいる牧師たちも料理好きである。柳井牧師、岸本牧師、皆さん講釈を垂れながら料理を提供する。
私もいくつかの定番がある。聖研後の愛餐会、らくなんクラブの「園長カレーの日」、NPOほっこりとの「カレーをみんなで食べる会」の時である。これは月1回ごとの行事であるが、その一つを紹介したい。
洛南では、水曜聖研を月1回する。釈義者は現在、韓亨模(丹後宮津)牧師が担当する。3月29日に開催したが、受難週を前にルカ22から受難の場面を学ぶ。因みに韓牧師は京大の研究科に籍を置き、日曜は宮津の奉仕、大学非常勤をし、郵便局の集配のバイトをと、忙しくしている。
参加者は、4つの教会から有志が集って、平均すると8名。ある者は聖研の終り頃に来ての参加であるが、30分の講解と30分の質疑、最後にはせわしいなかでも祈祷をもって終わる。
その後は愛餐の時をもつ。3月は「キリストの肉となるパン」と「キリストの血となるブドウ酒」をメインの愛餐である。4時ごろに買い出しに行き、2時間かけて料理を作る。この日はシチューとサラダを添え、パンとブドウ酒を用意した。料理をする者には何か決まった具材があるが、わたしが好むのは、チーズ、干しブドウ、リンゴである。教会3Fには小さな台所がある。ここで料理するが、一人料理する時は便利である。
8人の食欲は旺盛である。平均年齢は65歳位だと思うが、2時間を使って、食べ、飲み、談笑する。この日も8名。3本のワイン、6本の缶ビールが用意されるが、今回も空っぽになった。
この聖研が始まって、最初の釈義者は大平牧師であった。次に鄭牧師、韓牧師で3代目となると思うが、皆さん、それぞれに特徴のある釈義をされてきた。コロナ禍になって何回か愛餐は休んだが、続けてきている。
最近、「ふと、思う」ことに、この会合は、聖研なのか、飲んべーの「飲み会」なのか、と思う時がある。
ただ、みんな帰る時、満足して帰り、また、
次回も集まってくる。
楽しい時である。
(*参加者のなかには、飲まない方もいますが・・・・。)
ふと、おもふ 柳井一朗 2023年3月19日 (№7)
3月6日 大江野の花教会人見勝牧師葬式に出席した。
綾部市斎場には15年くらい前に、旧建物の時代に、葬儀で一度使用したことがあった。
25年前、大江野の花教会献堂式に、佐原英一牧師と出席した。
その後20年間、人見先生夫妻、大江野の花教会の教会員の方と親交を深めた。
田植え、草取り、収穫、栗拾い、蛍鑑賞、大江山同行、歳末餅つき、
大江野の花教会での礼拝、家庭集会、多くの若者を連れて訪問した。
20年間で200回以上訪問しているので、当方は人見先生との別れに際して、後悔、悔いがない。
最近は京都縦貫道を使うことはなく、行きは9号線から173号線、帰りは27号線から9号線経由で往復している。
通いなれた路だ。

2006年5月3日教区総会聖餐式配餐
生前、人見先生から次のようなことを言われた。
「夏、人が倒れるほどの暑さがないと、コメは育たない。」
「田植えしてから、毎日の温度の足し算で1000度になった頃がコメの収穫時期である。」
農業生活ではない私は、人見先生の生き方から多くを学んだ。
振り返れば、「広域伝道圏伝道」の実践をさせてもらえたと思う。感謝。
『ふと、思う』は、リレーエッセイです。(次回:井上勇一)
三笘の1ミリ 入 治彦 2023年2月19日 №6
昨年の11月から12月にかけてサッカーのワールドカップがカタールで開催されました。日本は優勝経験のあるドイツとスペインに勝利するという大金星を上げました。中でもスペイン戦の「三笘の1ミリ」といったことが話題になり、今回のワールドカップを象徴する印象的なシーンとしてサッカー界から評価されています。
三笘 薫選手のゴール際のラインを越えたと思われたところから挙げたクロスを田中 碧選手が入れたゴールは本当に面白いゴールでした。本人たちはラインの外に出てしまったか、内側だったか半信半疑だったようですが、日本側の観客は「ゴールだ!ゴールだ!」と叫び、審判も決めかねる様子でした。そこで、主審が手で四角の形をジェスチャーで表すと、ビデオ判定となりました。V A R(ビデオ・アシスタント・レフェリー)の判定では、一見外に出たようでも、1ミリだけラインに乗っていたということになり、ゴールと認定されました。
人間が人の目で横から水平に見ていた時、それはもうラインの外だったものが、V A Rの機械が上から垂直に写した時、ちゃんとラインの上に1ミリだけかかっていた。ボールの中にチップが入っているので、ゴールとかなり正確な結果が出たとのことです。
私はふと、イエスという人がゲネサレト湖で夜通し働いても不漁だった漁師たちに向かって「沖に向かって漕ぎ出して、網を降ろし、漁をしなさい」と声かけられた時の場面を思い出しました。魚とりにかけては玄人の漁師たちが素人のイエスの言葉に促され「しかし、お言葉ですから網を降ろしてみましょう」と応じたことも不思議ですが、その通りにしたところ、大漁だったといいます。
浅瀬で水平に投げる投げ網を使っていた時、魚を漁れなかったものが「沖」に出て命じられた通り、その網を上から下に垂直に降ろすように使ったところ、大漁だったという不思議。人間の水平的な目から見たらダメでも、神の垂直の視点から見たら捨てたものじゃない。それも「深み」に網を降ろした時の溢れる恵みの豊かさ。
パウロは記しています。「霊は一切のことを神の深みさえも極めます」そこには十字架に隠された神の奥義が語られているように思えます。
『ふと、思う』は、リレーエッセイです。(次回:柳井一朗)
号 外 2023年ご挨拶 Rev. Kishimoto
『はっぴょん・にゅー・いやー・2023!』
ぴょんぴょん撥ね跳ぶ一年でありますように!

夕焼け空の美しさ 菅 恒敏 2023年1月15日 №5
昨年の9月29日のこと、教団総会を終えての新幹線車中で、岐阜と滋賀の中間点当りで何気なしに車窓外を眺めた瞬間、驚きとともに夕焼け空のすごい眺めが飛び込んできた。右端から左端の視野一杯に延々と続く、真っ赤に燃えるような空のオレンジ色とその色を反射して光る雲の紫色が織りなす、とてもこの世のものとは思えないスケールの大さと美しさに圧倒され、しばらくの間その眺めが尽きるまで車窓の外を眺め続けていた。
この感動的な美しさとの遭遇により、相変わらず分断の続く3日間の教団総会での疲れが一気に吹き飛んでしまうとともに、すっかり夕焼け空の美しさに魅せられるようになった。
私は健康上の理由で散歩を心がけており、それ以来、散歩に出かけるときは夕焼け空を眺めるこがを楽しみになった。とくに秋から冬にかけては、気温が低く湿度も下がって、空の色が綺麗に見えるとも言われている。
冬に入ってとても寒い或る日のこと、たまたまその日の夕焼け空は、日の沈む地平線のオレンジ色に始まって、ピンク、紫、薄い青、群青色と上空に向けて続く色のグラデーションが見事な美しさであった。その美しさは、教団総会の帰途に眺めた夕焼け空のようなスケールの大きさはなかったが、色調の変化が織りなす繊細な美しさがまた違った光景を醸し出していた。
この眺めを前にして、地の端から上空に向けて色の変化を追いながら、群青色の上空に目を留めた瞬間、余りの美しさに空の中に吸い込まれるような錯覚を覚えると同時に、「ふと、思った」。この広大な大空の下、宇宙の中では人間はまさに塵に等しい小さな存在であることを、そしてその塵にも等しい人間が、こうして生きていることの不思議、否、生かされていることの有り難さを思わずにはおられなかった。空の広さ、美しさ、これこそは、万物の創造主たる神の業であり、万物が創られ、生かされていることを気付きを与えてくれるのであると。
その日以来、神様の存在が私にとってより身近に感じられるようになった。
『ふと、思う』は、リレーエッセイです。(次回:入 治彦)
気力が失せる 井上勇一 2022年12月18日 №4
11月22日にコロナ陽性の診断がでた。テジョン交流プログラムの一日目である。すぐに委員会メンバーに連絡をし、7泊8日のプログラムの担当部分をキャンセルした。大穴を空けてしまった申し訳なさと、迷惑をかけたことを悔やんだ。
ただ、プログラムは委員や関係者の努力と献身によって、成功裏に終了し、参加したテジョンのメンバー2人は、感謝の思いを伝えてきた。無理して、老体を鞭打たなくても、委員、関係者に任せればよいのにと、自らの反省の弁である。
今回、コロナ陽性者となり、11月27日に自宅待機から解放された。27日の礼拝は自主礼拝として行ったが、12月4日からいつものように礼拝をしている。ただ、何か気力が減退したのか、意気込みが湧きおこらないのである。
わたしも潮時を迎えたのか、ふと思う。そんな時、12月6日に「聖書を読み直す会」が洛南を会場に開かれ、出席した志賀勉さんがお菓子を下さった。そののし紙に「卒寿祝い」とあった。90歳で集会の準備をし、元気に飛び回る姿をみて、ふと思った「何でもやろうとする気力」が大切と。
前回の「ふと思う」に、80まで頑張りたいと書いた。健やかであればという条件付きであるが。50代や、60代前半は、空回りするような前向きに生きる姿があった。それが70代を過ぎることに、説教のあらすじが頭に入らない。言おうとする言葉が思い出せない。使い古した言い回しを何度も使う。そんなことを繰り返しながら講壇に立つ。そして、今や「気力が弱くなった」自分がいる。先が見えるような近況を考えると、志賀さんの旺盛に学ぼうとする姿勢には、感服するのである。
最近、「召命」という神の招きの言葉を よく考える。私たちは誰もが生涯に渡って 神の招きに応じていく、それが信仰というのであろう。ただ、自分の気力が希薄になると、召命観も希薄になるのかと自問する。そんなバカなことはないだろうと思うが、今までとは違った仕え方、働き方があるのかと、ふと思うのである。
『ふと、思う』は、リレーエッセイです。(次回:入 治彦)
ふと、おもふ 柳井一朗 2022年11月20日 №3
世紀をまたいで、かつて北米で8か月間滞在した。
クリスマスになると、空き地が切り倒されたツリーの即席販売所になる。
客は自分の車の天上にくくりつけてツリーを持ち帰る。
一月上旬、ごみ回収車が別途ツリーを引き取る。
このことをめぐって、環境だのああだのこうだと話題になる。
現在嘱託講師の身分で通う中学校、もうツリーが飾られている。
生徒に「早すぎる」と言うと、
「ハロウィーンが終わったらクリスマスだ」という。
聞いていてあきれる。

今の教会に住み込みで働きつづけて随分になる。
最初は毎年ツリーを買い求め、一月になると境内地に植えた。
その後温暖化と併せて、ツリーは巨大化している。反省しきり。
以後15年以上同一の木を庭に植えて、時期が来ると庭師と一緒に、
その木を掘り起こし礼拝堂に運び込む。
庭師によると、その木には大変なストレスがかかるという。
しかしこの木は主の降誕のために用いられる。
「強いられた恩寵だ」。
ウクレレ牧師 入 治彦 2022年10月16日 №2
先月テレビの『ケンミンショー』を見ていたら、琵琶湖がハワイ化しているという情報を取り上げていた。滋賀県近江舞子の付近では、おしゃれなハワイアンカフェやリゾートホテルが立ち並び、ウインドサーフィンやサップを楽しんでいる人がいるという。中にはハワイ出身滋賀在住、大柄でアロハシャツ着てウクレレかき鳴らしながら歌っていた本場の人も紹介していた。以前から夏になるとアロハシャツを着て、教区の会議にやって来るのも決まって滋賀の牧師たちだったなあ。琵琶湖にはサーフボードを乗せたステーションワゴンが似合うなどとも思う。
いや、ちょっと待てよ、京都南部地区にだっているじゃないか。アロハシャツ着て、ウクレレ鳴らし、漫談もどきの説教する人。ポニーテイルで、カントリーからフォーク、キャンプソング、讃美歌なんでもこなす器用なキ・シ・モ・ト牧師という人が。
私が初めて岸本さんの説教を聞いたのは、10年程前京都南部地区の新年合同礼拝だった。あの広い同志社教会(栄光館)で「お寺の鐘はゴーン(御恩)、教会の鐘はキミコンカイと鳴るが、行ってみるとガラーン」とかなんとか言ってた。あの時もウクレレやってたよね、たしか。
ウクレレはここ数年ブームでもあり、教区内でも数人ウクレレ得意の人がいるのを知っている。でも、牧 伸二みたいに「あ~あ~やんなっちゃった、あ~驚いた」といった調子でウクレレ鳴らし説教する人は他に知らない。
岸本さんは、昨年の4月から教区センター教会牧師のお役を引き受けてくださり、今年のイースターにはめでたく京都教区センター伝道所設立式を行うことができた。私はFacebookの動画配信の担当をしているが、彼について書いていると、なんだかキシモトテイストなるものが憑依してくるようだ。
関東人の私が「蚊に噛まれるじゃなくて、蚊は刺すもの」と言うと、関西人の妻から「関東の蚊は刺すのかも知れないけど、関西の蚊は噛むの!」と叱られ「ノリツッコミがまだできない」と言われる私は、これからも『既成の教会像に制約されない柔軟性やゆるさ』なるものを、スマホの画面越しに岸本牧師から学んでいく必要があるのかも知れない。
ふと、思う 井上勇一 2022年9月18日 №1
わたしは、10月で73になる。80まで頑張りたいと願い、毎朝の3キロ散歩をしている。でも忘れることも多く、週報を書いた後、会員に毎回間違いを指摘される。そんな中、「ふと思うこと」、それは「きみは今まで、何をしてきたか」との「声」である。
32から現場にでたので40年を過ぎたが、今まで人を気にし、人に気に入られるような話をし、祈ってきたのではないか、そんなことを「ふと思う」のである。聖書に描かれるキリストの思い、願いを語らず、神の意志、真理を語らず、人に気に入ることを語る自分を見るのである。
教会は「元気がない、力がない」と言われて久しいが、教会は弁解じみた言葉で自分を納得させる。牧師も同じである。「社会は教会に関心がないし、社会の豊かさは求めることが違う。」という。でも教会を見ると、教会は敷居が高く、地域と寄り添うことをしないし、求める者に優しくない。また、牧師も語ることが少なく、隣人に寄り添うことが少ない。「教会が社会に関心がない」と、己を振り返りながら「ふと思う」のである。
エゼキエルは「災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは・」と投げかけるが、ずっと気にしてきた言葉だ。「群れを養わず、己を養う」牧者よ、神の召命を忘れるな!と、そんな「声」を聴くのである。
以前、「神を愛することは、命を惜しまず仕えることだ」と聞いたことがある。よく教師になって巣立つ仲間に「あなたの召命観を大切にしてほしい。」と言い、さも「今の自分は神さまの召命に与かっている」ようなフリをする。「己を養って生きてきたもの」にもかかわらず、よくも「召命に生きている」などと言ったものだと自戒する昨今である。
上の言葉は、少々厳しく聞こえるが、昔の教会の様子を聞くと、「身を震わせながら路傍に立った」とか、「1軒1軒回りながら献金を募った」とか、「今月はこれで我慢してください」と言われながら、教会に仕える苦労話を聞く。昔と今の違いに驚き、自分であればどうであろうかと、身の引く思いをする。その教師の言葉に、「我が身を神に委ねる」とあった。神の召命に生きるということ、それは「神に我が身を委ねて生きる」ということか、ふと思うのである。
教会の週報に、よく「センター教会」のことを記すのであるが、どの教会が「主務」であるのか問われる。でも、「わたしに委ねられたこと」と受け止めたいと思っている。
最初のページに戻る 動画アーカイブス